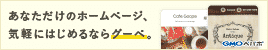ブログ
ピアノコンクールへの取り組み方と考え
こんにちは。長崎市のピアノ教室スタジオアポロ主宰の野中です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は保護者の皆さまからよくご質問をいただく「ピアノコンクール」についてお話ししたいと思います。
まず、ピアノコンクールとは何かというと、決められた課題曲や自由曲を演奏しその完成度を審査員が評価し点数や順位がつけられるものです。
演奏に優劣をつけるという点に戸惑われる方もいらっしゃるかもしれませんが、コンクールでは演奏の正確さや表現力など一定の客観的な基準に基づいて評価が行われております。
それではその点数は何によって決まるのかというと、まずは何より「楽譜を忠実に再現できているか」が重視されます。
何となくピアノ演奏というと個人の表現が注目されるような雰囲気がありますが、実はクラシック音楽は作曲家が遺した楽譜を正しく理解し再現することが前提となっています。
そのため、楽曲の時代背景を理解することが不可欠。
当時使われていた楽器(たとえばチェンバロやフォルテピアノ)や演奏様式、その時代における音楽の解釈や理論を学んだうえで、現代のピアノでどう表現するかが問われるのです。
例えばよく話で聞くような、バッハを弾いたら歌いすぎて点数が上がらなかった、装飾音符の入れ方が違った、などの点でいうと、歌ってはいけないのではなく抑揚の付け方が違うのです。メロディーラインがどれだけ綺麗であっても音楽の理論性を無視したデュナーミクを付けたりドラマチックに弾く必要はなく、音そのものを綺麗に自然に重ねていくことが必要になります。(音程の差を丁寧に付けていくイメージ)
また装飾音符が点数に関係するのか?というのは、もちろん使用する楽譜、そして師事してきた先生のバックグラウンドや国によって本当に細かいところは違うと思います。
ここ最近のコンクールを聴いていると装飾の入れ方の違いというより、筋が通っていれば(一貫性があれば)点数に影響なく聴いてもらえていると感じます。
(点数が気になる場合は入れ方というより丁寧に正確に入っているかが重要だと思います。)
コンクールではこのような背景に基づく「正確性」がまず点数に大きく関わります。
さらにそのうえで、ホールでの音の響かせ方や、演奏全体の完成度も大切な要素となります。
自宅や教室とは異なる広い空間で、どのように音を響かせるかはコンクールにおける重要な技術です。
電子ピアノよりも木のピアノ、出来ればグランドをというのは非現実的と思われますがクラシック音楽の演奏はグランドピアノを想定したもの。
ピアニスト反田恭平さんは、国際コンクールのために体重を増やして音の制御を改善したというエピソードもあるほど。
実は音の出し方ひとつに深い工夫が必要になります。
例えば毛筆の課題を出す時に、硬筆で練習を続けて当日筆で一発勝負で書きなさいと言われると、難しいという想像は出来ると思います。ピアノも同様。電子ピアノで練習して、そのままホールで理想の響きを作ることは不可能に近いのです。
そもそも電子ピアノと木のピアノは仕組み的に全く違うものであるということを知って練習に取り組むことは意識が大きく変わります。
こうした理由から、コンクールに向けたレッスンは、普段のレッスンとは異なるアプローチを取っています。
通常のレッスンでは、譜読みをして、音やリズム、強弱記号などを正確に演奏することが主な目標になりますが、コンクールに向けてはそれに加えて「音の発音の美しさ」や「時代背景に即した表現」など、より細かなニュアンスを追求していきます。
同じ一音でも、その弾き方ひとつで印象が大きく変わるため高度な表現力が求められるのです。
ピアノコンクールに参加する際、なぜ練習の大変さにフォーカスされがちなのかというと、特に小さなお子様にこうした要素を理解してもらい、音に反映させていくことには多くの時間がかかるからです。
きっとコンクールに対する練習でお子様や保護者様に見えているのはこの部分から。
ピアノ講師は日頃から楽曲の研究や自分のレッスンに取り組んでおり生徒さんに曲を渡す際には、既にある程度構成は考えた状態にあると思います。
研究も日々進んでいますから昔はこういう解釈で弾かれていたのが今では違う弾き方が一般的、など多くの選択肢からお子様の演奏をより魅力的に聴かせるための大きな枠組みは出来上がっている。
問題はそれをどのように生徒さんに伝えていくか、なのです。
もちろん、丁寧に説明しながら進めることを大切にしていますが、年齢によっては理解のスピードに限界もあります。
そのため、時には大人の演奏を「真似る」ことから始めることもあります。
どちらの方法を取るにせよ、一般的に想像されるよりも多くの時間がかかり、また練習の質と量も求められるため、ご家庭でのサポートも大変重要です。レッスン中の注意の頻度や密度も、通常のレッスンとは異なってきます。
当教室での取り組み方としては、まず第一に「卒業後に自走できる力を育むこと」を最終目標にレッスンしております。
そのためどんなに小さくてもできるだけ説明を重ねながらレッスンを進めています。
全ての音を理解して、発音すること。曲を構成すること。学ぶことでコンクール曲だけではなく普段練習していることにも、教室を卒業しても臨機応変に使っていけるようにとの想いがあります。
正直に申しまして、特に低年齢のお子様に対してはもっと上の賞を求めること、すなわちもっと厳しく詰めて練習させることも可能ではあるのですが、それによってピアノの練習が嫌いになってしまうリスクはかなり大きい。また幼児期に受けるコンクールでは努力の実感と賞の大きさのバランスが取れず後に「うまく弾けなくなってしまった」というような壁に直面することもあります。
小さい頃は理由が分からなくても先生の弾き方を「真似る」ことで弾けていたものが、年齢を重ねるごとに技術的・精神的な成長が追いつかなくなる場合もあるのです。
幼い頃に獲得した自己肯定感が、成長するにつれ劣等感の原因となりピアノから離れてしまった。そんな例は少なくありません。
このことから、年齢に合わせたフォローと負荷を見定めてとにかく保護者の方と本人の素敵な思い出になれば良いと、私自身は考えて取り組んでいます。
コンクールに取り組むお教室はたくさんありますが、レッスンでのバランス等先生の方針はそれぞれです。
将来コンクール参加を希望してピアノ教室を探されている保護者様はその辺りをご参考頂ければと思います。
練習の密度や回数、レッスン中の注意のレベルなども通常より高くなり、お子様にとってもご家庭にとっても「負荷」がかかることは事実ですので、参加ご希望でも取り組み方は慎重にご相談させていただいております。
当教室ではコンクールへ毎年挑戦する生徒さんもいらっしゃいますが、ピアノを習っていた記念に、一回だけ出てみようか?とお試しで参加される方も。それぞれの成長やご都合に合わせて無理なく取り組まれているようです。
コンクールへの参加をご希望の場合は、曲選びの段階から一緒に考えご家庭とのバランスを見ながら慎重に進めていきます。
どうぞいつでもご相談ください。
ピアノコンクールは、華やかな舞台に立ち努力の成果を発表できる貴重な機会です。
それまでの過程も含めて、きっとお子様の人生に残る大きな体験となることでしょう。
年間通して様々なコンクールが開催されますが、夏がシーズンの始まりになります。
教室でも少しずつ仕上げが始まりました。
今年も、生徒様それぞれのペースと個性を大切に、無理のない指導を心がけてまいります。